導入企業インタビュー
LMS活用で得られた「主体的な学習」と「社員同士の横のつながり」の強化。研修運営関連の業務負荷も8割軽減できた。次は「自社の企業風土」×「学びのDX」で自律学習の場をより充実させていきたい。
ナブテスコ株式会社 様
ナブテスコ株式会社
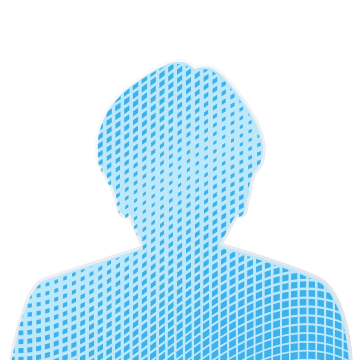
今回は、社員が自律的に学習を進められる学習環境の整備と学びのDX化に取り組んでおられる人事部ご担当者様にお話を伺います。
LMS導入の狙いは、1年間にわたる研修期間の中で、
“自律的に学習できる環境”を提供すること
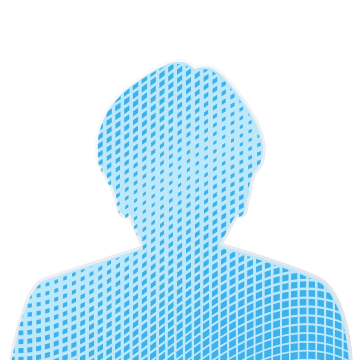
はい。この研修は当社に新卒で入社した社員のうち、製造現場で働く者を除いたメンバーが参加する研修です。新入社員研修で一緒だったグループ会社の社員が一同に会する機会にもなっています。年によって人数は違いますが人数は大体50名前後です。単発で1~2日で実施される研修とは異なり、入社1年目の10月から2年目にかけての1年間で実施します。
その研修に『ビジネスマスターズ®』を導入いただいたのが、ちょうど2年前でした。ビジネスマスターズを導入いただいた時、どのような背景や期待があったのか、改めてお聞かせください。
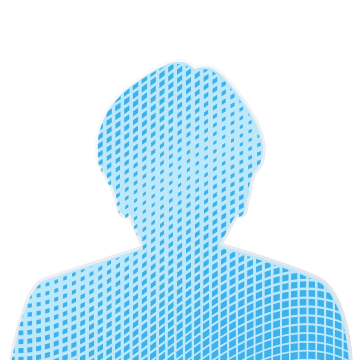
2020年のコロナ禍以降、対面での集合研修の実施が難しくなりましたが、それに加えて、当社には「学びの場を研修の場に限らない」「受け身ではなく、自律的かつ継続的な学びの場を提供していきたい」という意向がありました。ビジネスマスターズであれば、受講者が“自分で学習できる環境”を、研修と研修の間にも提供できると判断し、導入しました。
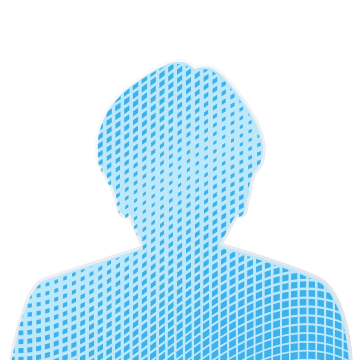
ビジネスマスターズを学習プラットフォームとして導入する前提で、プログラムの構成を貴社とご相談しながら検討しました。具体的には、これまで集合研修で行っていた講義の部分は映像教材を事前視聴し、10回前後実施していたリアルな集合研修をリアルとオンラインで4回実施する、課題の提出をプラットフォームで行う、といった変更を行いました。
当社の場合、全国に事業所が6つあります。普段、違う事業所の受講者同士だと、どうしてもコミュニケーションを取りにくいところがあります。しかし、本研修ではビジネスマスターズのチャットルームを使って、研修と研修の間のインターバル期間にもコミュニケーションを取りながら、研修課題などについて色々とディスカッションしていたようです。オンライン研修当日には、投稿されていた内容を話題にしたり、グループワークの際にも、チャット上で話し合ってきたことを引き合いに出しながら議論を進めたりする様子も見られました。
集合研修の数が少なくなったからといって過去の研修実績と比較してコミュニケーションの数や質自体が落ちたり、疎遠になったりすることなく、むしろつながりや連携が良くなっている面も見受けられました。これはビジネスマスターズが研修の場以外でのコミュニケーションの場としてしっかりと機能してくれたからだと考えています。
研修と研修の間を繋ぐ学習プラットフォームの導入で自律的に学び、
「学び合う」基盤を作ることができた
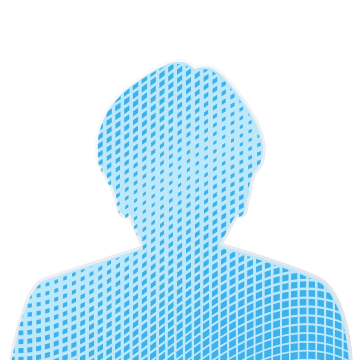
ビジネスマスターズ導入以前は、課題を事務局宛てにメールで提出するだけですから、受講者としては「自分が書いて、提出して終わり」という状況でした。それを、課題を「投稿する」ことに加えて、他の受講者の投稿に対してリアクションしたり、フィードバックコメントを投稿したりすることを研修の修了要件にしました。
受講者は自分の提出物に対して誰かからリアクションをもらったり、他の受講者の提出状況や内容を知ることができるようになりました。このように受講状況が可視化されたことで、事業所や部署内に複数のメンバーがいるところでは、出していない人がいると受講者同士で声をかけあっていたようです。この研修の設計であれば、特別の事情がない限り「事前課題に何も取り組まずに研修に参加する」といったこともありませんし、事前・事後課題の提出状況も以前より非常に良くなりました。
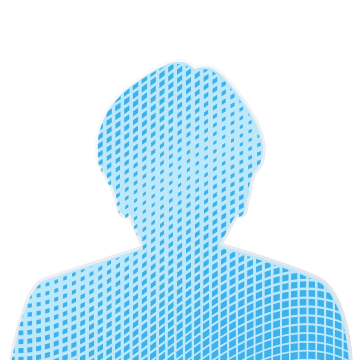
当社の研修・教育におけるスタンスとして、強制することで何かを達成させる、ということはしたくない、という方針があり、基本、見守るようにしています。
本研修ではまさに期待通り、ある程度のところまで自然な学び合いに任せることができました。受講者が互いに協力し合いながら課題や研修に取り組む様子からも、自律学習を始める”きっかけ”を作ることができた、と見ています。
ビジネスマスターズの導入で、コロナ禍以降に増え続けた研修管理業務の負荷が8割減
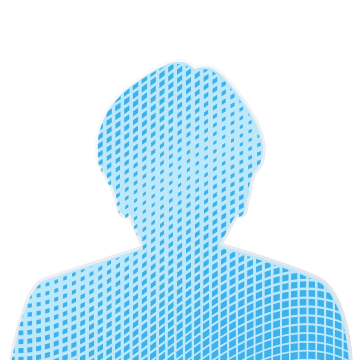
コロナが明けてから、特に人的資本経営が注目されたこともあり、当社でも研修の数は増えました。それでも事務局の人員は増やすことなく、少ない人数でかなり多くの研修を企画担当する状況でした。オンライン化が進んだので、増えても対応できるようになってしまった、とも言えます。一方で、オンラインでも対面でも、1つの研修に対する企画や事務作業の量はあまり変わりません。例えば、関連する事前・事後課題の回収はeメールとエクセルによるアナログ管理でしたので、非常に手間がかかっていました。
それが、ビジネスマスターズを導入したところ、回収状況はパソコンの画面上で簡単に、一目で確認できるなど、研修運営に関する事務作業のほとんどを一括してビジネスマスターズに任せられるようになりました。これまでの作業量を10かかっていたとすると、2程度まで軽減された印象です。1年にわたって実施するこの研修の運用においては、もう、これナシでは成り立たないと感じるくらい、頼りにしているところです。
社員が、自分で学ぶべきことを探したり、
適切なタイミングで、適切なレベルの学習ができるように支援する
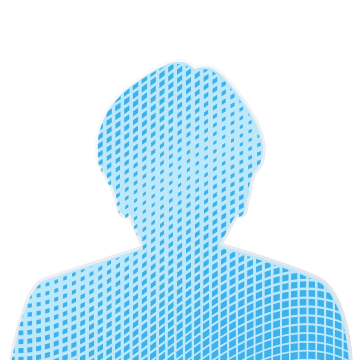
当社でもこの入社1~2年目という年次に対して「自律的な学習をできる人財になって欲しい」と期待しています。この年次の社員は、他の階層と比べて身につけるべきスキルや知識、考え方などが多く「どのタイミングで何を研修し、身につけてもらうべきか」非常に悩ましい部分があります。遅すぎず、早すぎず、適切なタイミングで、業務に必要な知識・スキルを身につけてもらいたいと考え、研修担当として注力しています。
特に、1年間にわたる研修プランを自律学習の要素を加えた形で再設計するにあたり、どの順番で、どの内容を動画でカバーし、研修では何を学んでもらうのか、事前・事後課題にどの動画を選定するかなど、貴社にご相談しながら学習設計することができ、大変心強かったです。
研修期間中はもちろん、受講者が研修後も学びを継続できるよう、最後の集合研修日が終わってから最低1か月前後の期間、ビジネスマスターズ上で動画を視聴できる研修設計を推奨しています。
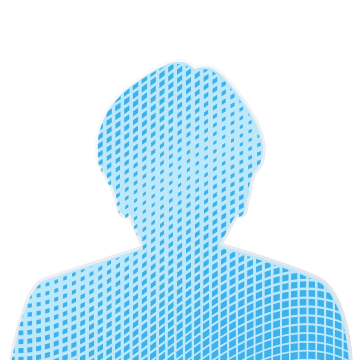
当社の本研修も、1年間にわたる研修の、最後の集合研修が終わってから約1カ月半は自由に視聴できるように設定いただいています。この設定については研修日の最後にアナウンスするようにしていますが、中には、アナウンスを待たずに「他にもあるみたいですが、見てもいいですか?」と聞いてくれる受講者もいます。
当社としては、全社的な取り組みとして、このように主体的に学習していける人材を増やしていきたいと考えていて、現在、自律学習やリスキリングに取り組んでいただくための環境整備の施策として、公募形式で他社の動画見放題サービスを視聴できるようにもしています。
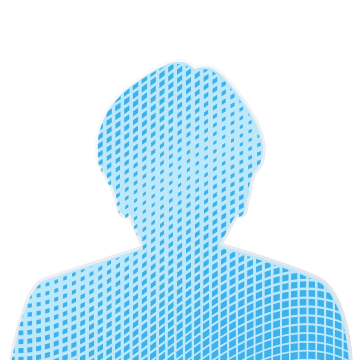
当社では現時点、ビジネスマスターズは研修と紐づけて利用したいと考えています。特に、ビジネスマスターズを導入したこの年次の場合は、仕事の進め方でも「言われたものをそのままこなす」といった傾向があるなど、自分のレベルや特性に合った動画を自分で探すのがまだまだ難しい、といったところがあります。だからこそ、指定された動画を視聴するだけでなく、自律的に視聴学習を進められるように学習環境を整備したい。ビジネスマスターズには質の高い動画が厳選して搭載されていて、手入れが行き届いている印象があります。貴社が動画の内容とレベル感をすべて把握されているので、研修内容を踏まえ、適切な推奨動画を提示することもできており、学習を推奨する環境として非常に安心感があります。
他社サービスは自律学習やリスキリングのために、社員が希望すれば誰でもいつでも利用できるようにしています。視聴のきっかけは他の社員からの口コミが多いようです。最近では上司やOJT担当者が特定の動画を「視聴させたい」ということで利用されることもあるなど、活用が広がりつつあります。
見放題サービスの場合、搭載されている沢山の動画の中から社員に自ら選んで学習してもらう必要があり、そこがボトルネックになっている状況が見えているので、人事部としては、自律学習を支援するべく、ラーニングパスのような情報を提供しています。
「学びのDX」の今の目的は「データ活用」ではなく、
社員が自律的に学べる「環境の整備」。
カンパニー制だからこそ、社員が求める「横のつながり」のある研修を企画したい。
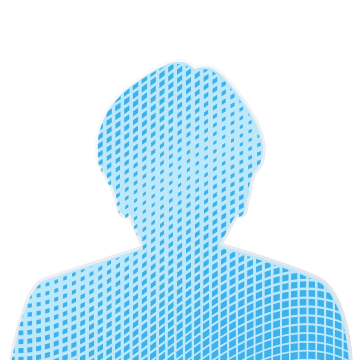
ハイパフォーマーの特徴やコンピテンシーに関するデータは非常に重要で欲しいところではあります。ですが、今の時点では、まずは自律的に学べる場をしっかりと提供していく。その後に、学習ログと受講者のパフォーマンスやコンピテンシーと結びつけるような分析をするといったデータ活用のフェーズに入っていくのかもしれません。そのためのデータの蓄積は必要で、データがあれば、今後、いろいろなところで活かせると考えます。
現時点ではこうした領域において、すべてをデータで定量的に測ることは難しいといった点について、経営層からも理解を得られています。当社では昔から「人を大事にする」という社風が根付いており、教育に力を入れています。加えて、カンパニー制のため縦割り文化になりやすいところがあるので、研修を横連携のメリットとして意識している部分があり、それで研修を増やしている、それをよしとしているところがあります。研修のアンケートでも受講者から高い評価をいただくコメントは「普段の業務ではつながらない、違う事業所の人の意見が聞けた」というものです。そこはどの階層でも受講者が非常に求めているところですので、引き続き、効果的な施策を企画・実施したいと思っています。
今回ビジネスマスターズを導入することで、集合研修の開催頻度を減らしながらも、受講者間のコミュニケーションが活性化し、事業所が異なる受講者同士もコミュニケーションが取りやすくなりました。また、事務局の業務量も大幅に軽減し、効率的な研修運営ができるようになりました。人事部として目指していた「自律学習ができる環境の整備」という点においてもビジネスマスターズは本研修において良く機能してくれていたと考えており、導入した意思決定と費用対効果に対して、経営層からも高い評価を得ています。
ナブテスコに根付く“ワイガヤ”文化と“学びのDX”で、「横のつながり強化」「自律学習」「リスキリング」を加速させる
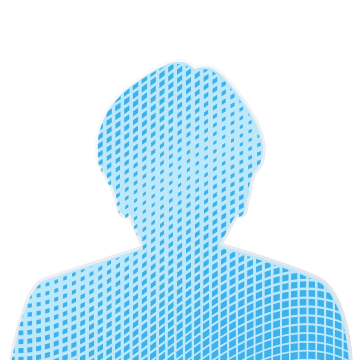
当社では“ワイガヤ”と呼ばれる「話し合いの場」を持つ組織文化が企業風土として定着しています。コロナ禍よりもずっと以前から年に1〜2回は必ず実施していて、例えば毎年4月から5月にかけてはナブテスコウェイについてのディスカッションをしています。
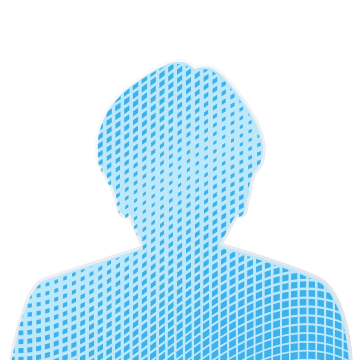
はい。例えば、当社のナブテスコウェイの場合、それ自体はどの職場にも当てはまるように抽象度が高くフワッとしたものにしています。これをどのように解釈して上手く「自分事に落とし込むか」は各職場にあえて任せて、話し合っていただきます。各職場では、いつもの定例会議の中で「ワイガヤの時間を取りましょう」といった形で実施されることが多いようです。
このような場合、映像教材による知識・スキルのインプットと演習やロールプレイ、そして現場実践を繰り返す研修プログラムを実施できると非常に効果的ですが、研修以外のアプローチとして、「年に1度のキャンペーン」活動のような形で、定期的に話し合う時間をカジュアルに持たせる、という貴社のお取り組みは、他の企業様にとって非常に参考になるお話だと思います。
今回お話を伺って、貴社には既に、共に語り、学び合う組織文化、組織風土があり、横のつながりを大切に考えていらっしゃることが非常によく分かりました。だとすると、貴社の“ワイガヤ”の場に、学びのDX=プラットフォームを取り入れていただいたら、横のつながりも、自律学習やリスキリングも、さらに促進できる、そんな可能性があるのではないか、と考えました。
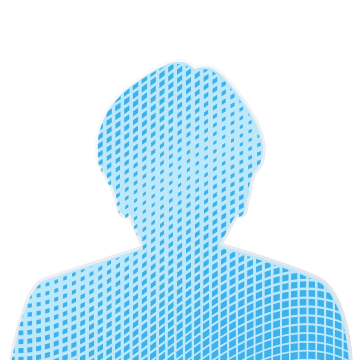
確かにそうですね。当社の社員数のボリュームゾーンとなる製造現場では、ワイガヤは日常的に行う、当たり前の行動ですし、まさに横のつながりは強化していきたいところですので、検討してみたいと思います。
1点検討の余地があるとすれば、製造現場の社員はかなり専門的な知識や技術を身につける必要があり、専門性を磨いていきたいというキャリア志向もあります。ですから、ビジネスマスターズで学べるような「一般的なビジネススキルの習得」は階層別研修で扱うようにしています。